買い物前に、今日のタイムセールをチェック
いつもの食材や気になっている調味料を買う前に、
そのとき実施されているタイムセールを軽くのぞいておくと、
まとめ買いのタイミングの目安になります。
気になる人は、下のリンクから公式ページをチェックしてみてください。
※セール内容・価格・在庫状況は日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
結論の要点:お歳暮の御返しは基本は不要。まずは到着の連絡とお礼を伝えましょう。どうしても気持ちを形にしたいときは、時期に合わせた表書き(のし)と相手に気を遣わせない金額感で選ぶのが安心です。年内に間に合わなければ「御年賀」、松の内(地域差あり)を過ぎたら「寒中御見舞/寒中御伺」、立春を過ぎたら「余寒御見舞」に切り替えるのが一般的です。
どれにしようか迷ったら、今の人気をのぞいてみる
調味料やお菓子、キッチン用品など、似たような商品が多いときは、
売れ筋ランキングで「よく選ばれているアイテム」を見ておくと、
候補をしぼるときのヒントになります。
※ランキングや取扱商品は入れ替わる場合があります。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
この記事でわかること(目次)
- お歳暮の御返しは必要?まずやること
- いつまでに贈る?「時期と表書き」早見表
- のし・水引・内のし/外のしの基本
- 相場はいくら?何を贈る?(選び方のコツ)
- 喪中・ビジネス・会社宛のときの注意点
- そのまま使える「お礼状」テンプレート
- よくある質問(Q&A)
お歳暮の御返しは必要?まずやること
原則:御返しは必須ではありません。お歳暮は「日ごろのお礼」を年末にお伝えするご挨拶。いただいた側はまず到着の報告と感謝を伝えるのが先。阪急百貨店の解説でも、原則は品での御返しは不要としており、先に礼を尽くす姿勢が推奨されています。
お礼を伝えるタイミングはなるべく早く(目安:到着から3日以内)。ハーモニックやアンティナのガイドでも、3日以内を目安に丁寧にお礼を出すことが勧められています。電話やメールでも構いません。
ただし、「毎年のやり取りで返したい」「どうしてもお礼の品を添えたい」など、関係性によって返礼を選ぶのは問題ありません。その場合は後述の「時期と表書き」と「相場」を守りましょう。返礼相場はのちほど解説します。
買い物リストを決めたら、セールもちらっと確認
いつもの食材や日用品を買うときに、
そのタイミングで実施されているタイムセールを一緒に見ておくと、
まとめて注文するきっかけになることがあります。
気になる人は、以下から公式のタイムセールページをのぞいてみてください。
- ストック品や日用品を買う予定がある
- その日のお買い物の「ついでに」セールも見ておきたい
※セール内容・対象商品・価格などは日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
いつまでに贈る?「時期と表書き」早見表
年内にお返しの手配が難しいときは、表書きを切り替えるのがマナーです。日本郵便(JP)の解説や主要ギフトサイトの基準をもとに、地域差や暦も踏まえた早見表を作りました。
| 届く/贈る時期 | 表書き(のし上) | 補足 |
|---|---|---|
| 年内(目安:12/20〜25頃までに到着) | 御歳暮 | 地域差はありますが、12月20日頃までに届くように手配するのが無難。遅れそうなら年明けに切替。 |
| 年明け〜松の内まで 関東:1/1〜1/7、関西:1/1〜1/15 目安 |
御年賀 | 手渡しは1/2以降が一般的。松の内の期間は地域で異なるため、先方地域に合わせる。 |
| 松の内後〜立春まで | 寒中御見舞/寒中御伺 | 松の内終了後〜立春の前日まで。2025年の立春は2月3日です。目上には「寒中御伺」を使うことも。 |
| 立春後(〜2月末目安) | 余寒御見舞/余寒御伺 | 立春を過ぎたら切替。2月末までの便宜的な目安が紹介されています。 |
参考:2025年の立春は2月3日(月)(国立天文台「暦要項」)。したがって寒中見舞いは概ね1/8〜2/3、以降は余寒見舞いが目安です。
のし・水引・内のし/外のしの基本
水引は紅白の蝶結び(花結び)+のし有りが一般的。包装の内側にのしを入れる「内のし」、外から見えるように掛ける「外のし」は、次のように使い分けると迷いません。
| 種類 | 見え方 | 向いている場面(目安) |
|---|---|---|
| 内のし | のしが包装紙の内側に入る | 宅配で送る/控えめにしたいとき(のし汚れ防止・名目を強調しすぎない) |
| 外のし | のしが包装紙の外側で見える | 手渡しで渡す/名目をはっきり見せたいとき(挨拶の趣旨を伝えやすい) |
年明けに贈る場合は、のし上(表書き)を「御年賀」→松の内後は「寒中御見舞/寒中御伺」→立春後は「余寒御見舞」へ。のし名目の切替は上の早見表を参照してください。
どれにしようか悩んだら、「今よく選ばれているもの」を見る
調味料・お菓子・キッチン用品など、似た商品がたくさんあると
どれを選ぶか迷ってしまうこともあります。
そんなときは、売れ筋ランキングで「どんな商品がよく選ばれているか」
全体の雰囲気をつかんでおくと、候補をしぼりやすくなります。
・人気のある商品をざっくり眺めたい
・他の人がどんなアイテムを選んでいるのか参考にしたい
※ランキング・取扱商品は入れ替わることがあります。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
相場はいくら?何を贈る?(選び方のコツ)
相場の目安:お歳暮の返礼は半額〜同額「以下」が目安とされます。高額になりすぎるとかえって気を遣わせるので、ほどよい金額感を意識しましょう(まずは礼状→必要なら返礼)。
選び方の基本:相手に負担がかからない「消えもの」(食品・飲料・日用品)やカタログギフトは無難。家族構成やアレルギー、保存場所も配慮すると安心です。年明けに贈るときはのし名目と時期の整合を最優先に。
- 年内に間に合わない → 御年賀(松の内まで)へ切替。
- 松の内を過ぎた → 寒中御見舞/寒中御伺へ。
- 立春後 → 余寒御見舞へ。
ビジネスでの配送可否:御年賀は本来「年始回りの手土産」とされ、宅配はマナー上避けると解説する資料もあります。訪問が難しい場合は季節の挨拶状+適切なのし名目で対応する方法が紹介されています。運用は先方の社内ルールに合わせ、無理のない形を選びましょう。
喪中・ビジネス・会社宛のときの注意点
- 喪中:お歳暮や御返し自体は差し支えないとされますが、忌中(四十九日前後)は時期をずらす配慮を。年明けは御年賀を避けて「寒中見舞い」へ切替が無難です。
- ビジネス・取引先:まずは礼状(到着報告)→必要に応じて相場内で返礼。贈答の可否・名義・費用負担は社内規程に従いましょう(会社宛に届いた場合は共有・保管ルールの確認を)。
- 地域差の配慮:松の内は関東:1/7まで/関西:1/15までが一般的。先方地域に合わせるのが安心です。
そのまま使える「お礼状」テンプレート
届いた当日〜3日以内に送れる、短文テンプレを用意しました(コピペ→宛名と日付を差し替えてOK)。
【個人宛・はがき/メール】このたびは結構なお歳暮の品をお送りいただき、誠にありがとうございます。さっそく家族みなでありがたく頂戴いたしました。お気遣いに心より感謝申し上げます。寒さ厳しき折、どうぞご自愛のうえ良いお年をお迎えください。 【ビジネス宛・メール/書状】 平素よりお世話になっております。お歳暮の品を頂戴し、誠にありがとうございました。 先に到着のご連絡を申し上げます。ご厚意に深く感謝し、今後とも変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます。 略儀ながらメールにて御礼申し上げます。
よくある質問(Q&A)
Q1:結局、御返しは必要ないの?
A:基本は不要ですが、礼状は早めに。関係性によっては返礼を選んでもOK。その際は半額〜同額以下目安で、時期と表書きを合わせましょう。
Q2:12/25を過ぎてから届いた・返したい。表書きは?
A:年明けに「御年賀」(松の内まで)、松の内後は「寒中御見舞/寒中御伺」、立春後は「余寒御見舞」へ。2025年の立春は2月3日です。
Q3:のしは何を選べばいい? 内のし・外のしは?
A:紅白の蝶結び+のし有りが基本。宅配=内のし/手渡し=外のしが目安です。
Q4:会社宛に大量に届いた。御返しは?
A:まずは代表名で礼状。返礼の要否や方法は社内規程に合わせて決裁。品は消えもの中心で共有しやすいものが無難です。一般論であり、各社ポリシーに従ってください。
Q5:具体的な「いつまでに出せば間に合う」目安は?
A:御歳暮は12月20日頃までに到着を目安に動くと安心。遅れたら表書きを切替。年賀状の運用や松の内の期間は日本郵便の案内を参考に。
チェックリスト(迷ったらここだけ確認)
- Step1:届いたら当日〜3日以内にお礼(電話/メール/手紙)。
- Step2:返礼するなら半額〜同額以下を目安に、消えもの中心で。
- Step3:年内→「御歳暮」/松の内(関東1/7・関西1/15)→「御年賀」。
- Step4:松の内後〜立春(2025年は2/3)→「寒中御見舞/寒中御伺」。立春後→「余寒御見舞」。
- Step5:のしは紅白蝶結び+のし有り。宅配=内のし/手渡し=外のしが目安。
関連情報(検索ニーズの高いキーワードもカバー)
- 「御年賀は郵送できる?」…本来は年始回りの手土産の性格が強く、宅配は避ける解説があります。訪問が難しい場合は、季節の挨拶状+適切なのし名目に切替えるのが無難。
- 「一度きりの返礼にしたい」…お礼状内で「今後はどうぞお気遣いなく」のひと言を添える/のしを「御礼」や「感謝」にする、といった案内もあります。
- 「松の内の地域差」…関東は1/7、関西は1/15が一般的。先方地域基準に合わせる。
まとめ:礼状→時期に合う表書き→ほどよい金額感で、気持ちよく
お歳暮の御返しは不要が基本。ただし、礼状は早めに、返すなら時期と表書きを合わせ、半額〜同額以下で相手に負担をかけない選び方を。2025年の立春は2月3日なので、松の内後は寒中見舞い、立春後は余寒見舞いに切替えれば安心です。
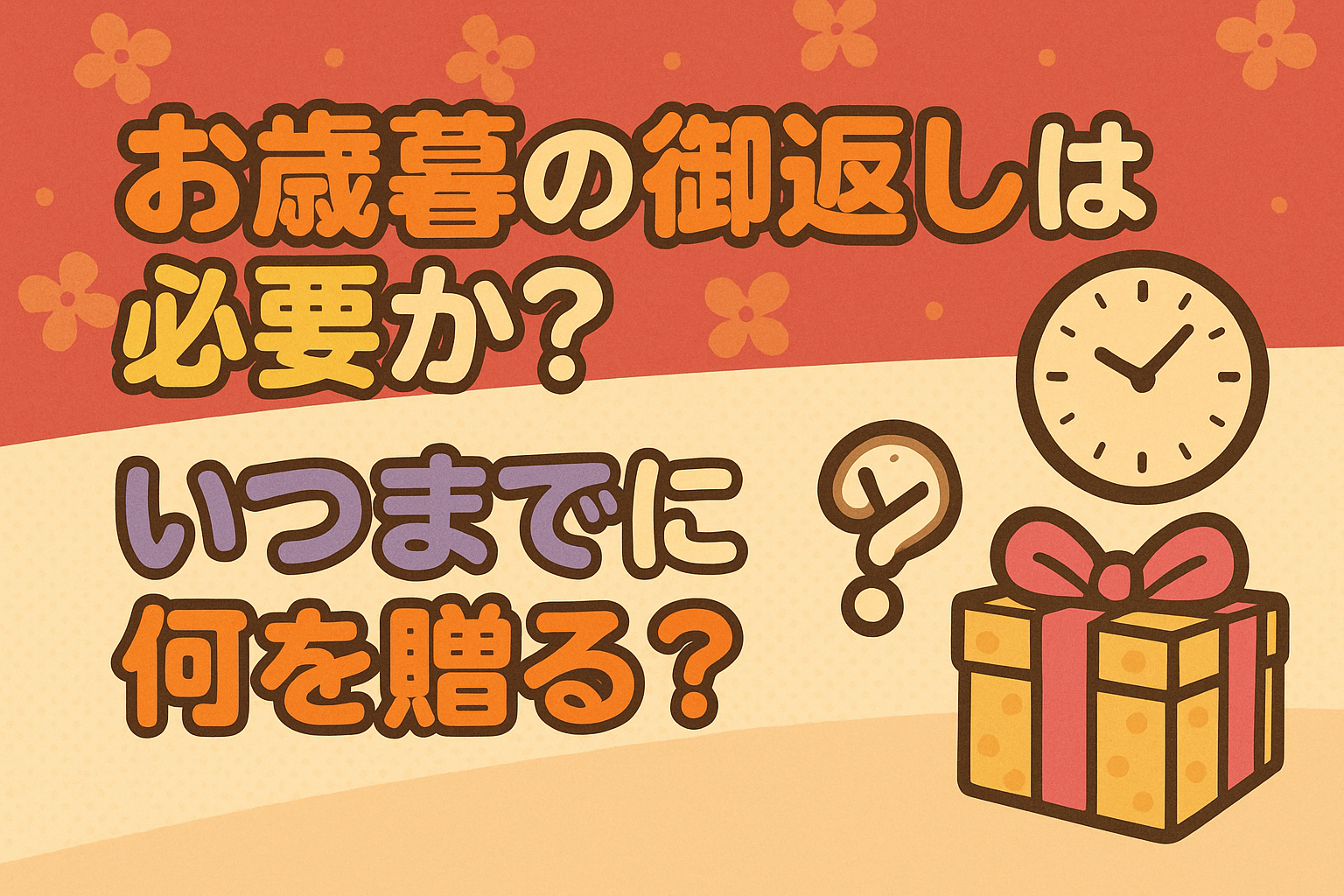

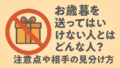
コメント