買い物前に、今日のタイムセールをチェック
いつもの食材や気になっている調味料を買う前に、
そのとき実施されているタイムセールを軽くのぞいておくと、
まとめ買いのタイミングの目安になります。
気になる人は、下のリンクから公式ページをチェックしてみてください。
※セール内容・価格・在庫状況は日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
先に結論。
「法令・規程で受領が禁じられている人」「職場方針で受け取りを断っている組織」「医療・教育など利害や公平性の配慮が特に必要な相手」「忌中(四十九日まで)」は、基本的に“送らない”判断が無難です。迷ったら、相手の規程を確認→送れない場合は寒中見舞い・手紙で配慮が安心です。国家公務員等は利害関係者からの贈答が禁止され、病院や学校でも職員への贈答を辞退する規則が明示される例があります。喪中は基本的に贈っても差し支えないとされますが、忌中は避けるのが一般的です。
- 結論:送らない判断が正解になる場面
- 第1章|お歳暮を送ってはいけない人とは(代表例と理由)
- 第2章|「送ってはいけない」をどう見分ける?(チェック方法)
- 第3章|喪中・忌中の正しい対応(のし・時期・言葉)
- 第4章|ビジネス実務チェックリスト
- 第5章|送れないときの代替案
- 第6章|ケース別Q&A
- まとめ
どれにしようか迷ったら、今の人気をのぞいてみる
調味料やお菓子、キッチン用品など、似たような商品が多いときは、
売れ筋ランキングで「よく選ばれているアイテム」を見ておくと、
候補をしぼるときのヒントになります。
※ランキングや取扱商品は入れ替わる場合があります。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
結論:送らない判断が正解になるケース
- 公務員・政治関係者など…利害関係者からの金銭・物品の贈与は名目や金額の多寡を問わず禁止。お歳暮も対象になります。
- 取引先でも「虚礼廃止・贈答禁止」方針の組織…企業側のコンプライアンスで受領不可の規定があるケース。事前確認が確実です。
- 医療機関・学校・公的機関など…公平性や誤解防止の観点から、職員への謝礼・贈り物を辞退と明示する規則が広く見られます。
- 相手(または自分)が忌中…四十九日が明けるまでは時期を外すのが無難。年明けは寒中見舞いに切り替えます。
第1章|お歳暮を送ってはいけない人とは:代表例と理由
1-1 公務員・政治関係者(受領禁止のため)
国家公務員倫理法・倫理規程では、利害関係者からの金銭・物品の贈与を受けてはならないと明記されています。名目が「お歳暮」「お中元」「手土産」でも基本は同じです。判断に迷う個別事例(市販菓子・観戦チケット等)も禁止行為として整理されており、“通常の社交儀礼”の例外に当たらない限り受領不可です。
1-2 取引先でも「虚礼廃止・贈答禁止」を掲げる企業・団体
最近は、形式的な贈答を避けるため受領禁止・虚礼廃止を掲げる法人が増えています。自社の贈答慣行に沿っても、相手が受け取れないことはあり得ます。事前に総務・広報・担当者へ受領可否を確認し、NGのときは代替の挨拶へ切り替えましょう。
1-3 医療機関・学校・公的機関(個人宛の贈答は原則NGが多い)
病院では、職員への謝礼・贈り物は受け取れないとする院内規則を公開している例があります。教育現場でも、保護者等から教職員への金品の受領を禁止するルールを教育委員会が設ける例が見られます。現場の公平性と公正さを守るため、個人宛の贈答は控えるのが安心です。
1-4 相手(または自分)が「忌中」のとき
喪中(服喪期間)そのものは贈っても差し支えないとされますが、忌中(四十九日)は避けるのが一般的です。お歳暮時期に忌中が重なる場合は時期を遅らせるか、年明けに寒中見舞いで配慮します。
買い物リストを決めたら、セールもちらっと確認
いつもの食材や日用品を買うときに、
そのタイミングで実施されているタイムセールを一緒に見ておくと、
まとめて注文するきっかけになることがあります。
気になる人は、以下から公式のタイムセールページをのぞいてみてください。
- ストック品や日用品を買う予定がある
- その日のお買い物の「ついでに」セールも見ておきたい
※セール内容・対象商品・価格などは日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
第2章|相手の「送ってはいけない」をどう見分ける?
チェックの手順
① 相手組織の公式サイト(コンプライアンス/贈答方針)を確認。
② 担当者・総務へ受領可否を問い合わせ。
③ 可否と根拠を記録(メール保存)。
④ 受領不可なら寒中見舞い・手紙・御礼状へ切替。
2-1 企業・団体のコンプライアンス掲示を探す
「贈答」「虚礼廃止」「受領辞退」などのキーワードで公式サイトを確認します。最近はニュースリリースやカスタマー向けFAQに方針が記載される例もあります。わからない場合は担当者に可否を確認しましょう。
2-2 公務員・公的機関は「利害関係」があるかで判断
許認可・補助金・契約などの関係がある場合、利害関係者に該当します。名称が「お歳暮」でも贈与の受領は禁止です。
2-3 医療・介護・学校の現場ルール
病院の院内規則や入院案内、学校・教育委員会の行動規範に贈答の受領禁止が明示される例があります。掲示や配布文書の確認が有効です。
2-4 忌中・喪中の把握と配慮
年賀欠礼はがきや訃報で喪中・忌中がわかる場合は、忌明け後に贈る、または寒中見舞いへ。表現・のしも配慮します(後述)。
第3章|喪中・忌中での正しい対応(のし/時期/言葉)
3-1 のし・かけ紙の選び方
- 相手が喪中:紅白ののしは避ける。無地の奉書紙や白い短冊で「御歳暮」の表書きにし、落ち着いた包装に。
- 自分が喪中:同様に華美なのしは控えめに。状況により無地短冊で。
3-2 タイミングと「寒中見舞い」への切替
年内に間に合わなければ、松の内明け(一般に1/8)~立春前日(概ね2/3〜4)に寒中見舞いとして贈ります。地域により松の内の期間に差があります(関西などは1/15とする地域あり)。
3-3 メッセージの書き方(例)
「ご多忙の折、日頃のご厚情へのお礼として心ばかりの品をお届けいたします。
華美にならぬよう失礼のない形にてお送りいたしますので、ご笑納ください。どうぞご自愛くださいませ。」
※弔意やお祝いを強く連想させる表現は避け、感謝と配慮を簡潔に伝えます。百貨店の解説でも表現・体裁の配慮が案内されています。
どれにしようか悩んだら、「今よく選ばれているもの」を見る
調味料・お菓子・キッチン用品など、似た商品がたくさんあると
どれを選ぶか迷ってしまうこともあります。
そんなときは、売れ筋ランキングで「どんな商品がよく選ばれているか」
全体の雰囲気をつかんでおくと、候補をしぼりやすくなります。
・人気のある商品をざっくり眺めたい
・他の人がどんなアイテムを選んでいるのか参考にしたい
※ランキング・取扱商品は入れ替わることがあります。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
第4章|ビジネスでの判断と実務チェックリスト
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 受領可否 | 相手企業の贈答・受領方針(虚礼廃止・受領禁止)を確認。 |
| 法令順守 | 公務員等は利害関係者からの贈与禁止(名目や金額に関係なく)。 |
| 記録 | 問い合わせメール・電話メモを保存。後の説明責任に備える。 |
| 継続性 | 前年実績があっても、相手方針の変更がないか毎年確認。 |
| 代替手段 | 受領不可なら御礼状・寒中見舞い・寄付報告などへ切替。 |
第5章|送れないときの「代替案」
- 寒中見舞いの品+短い手紙…松の内明け~立春前日が目安。
- 御礼状のみ…医療・学校等で受領不可のときに適切。
- 社内共有の謝意表明…取引先が受領禁止のとき、年度末の実績レポート等で感謝を明記。
第6章|ケース別Q&A
Q1:病院の先生にだけ個人宛で贈りたいのですが?
個人宛の贈答は辞退とする病院規則が明示される例があり、トラブル防止の観点からも避けるのが安全です。どうしても感謝を伝えたいときは、手紙や病院宛てのメッセージなど、院内方針に沿う方法で。
Q2:取引先が「虚礼廃止」。部署宛て共有品ならOK?
受領可否は相手方の規程が最優先。部署宛てでもNGな場合があります。事前確認のうえ、不可なら寒中見舞い・御礼状へ。
Q3:相手が喪中。のしはどうすれば?
紅白ののしは避け、無地の奉書紙・短冊で「御歳暮」等の表書きに。年明けにずれたら寒中見舞いに切替が無難です。
Q4:忌中にどうしても贈る必要があるときは?
確実な情報は確認できませんでした。基本は忌明け後、または寒中見舞いへの切替が案内されています。やむを得ず判断する際は、先方のご意向と宗教観・社内規程を優先してください。
まとめ|「相手の規程と状況 > 慣習」。迷ったら確認と配慮を
お歳暮は感謝の気持ちを形にする習慣ですが、法令・規程・状況によっては「送らない」が正解になります。
公務員等は受領禁止、企業は虚礼廃止、医療・学校は辞退が多い、そして忌中は避ける。不明なときは事前確認し、寒中見舞い・御礼状で誠意を示しましょう。
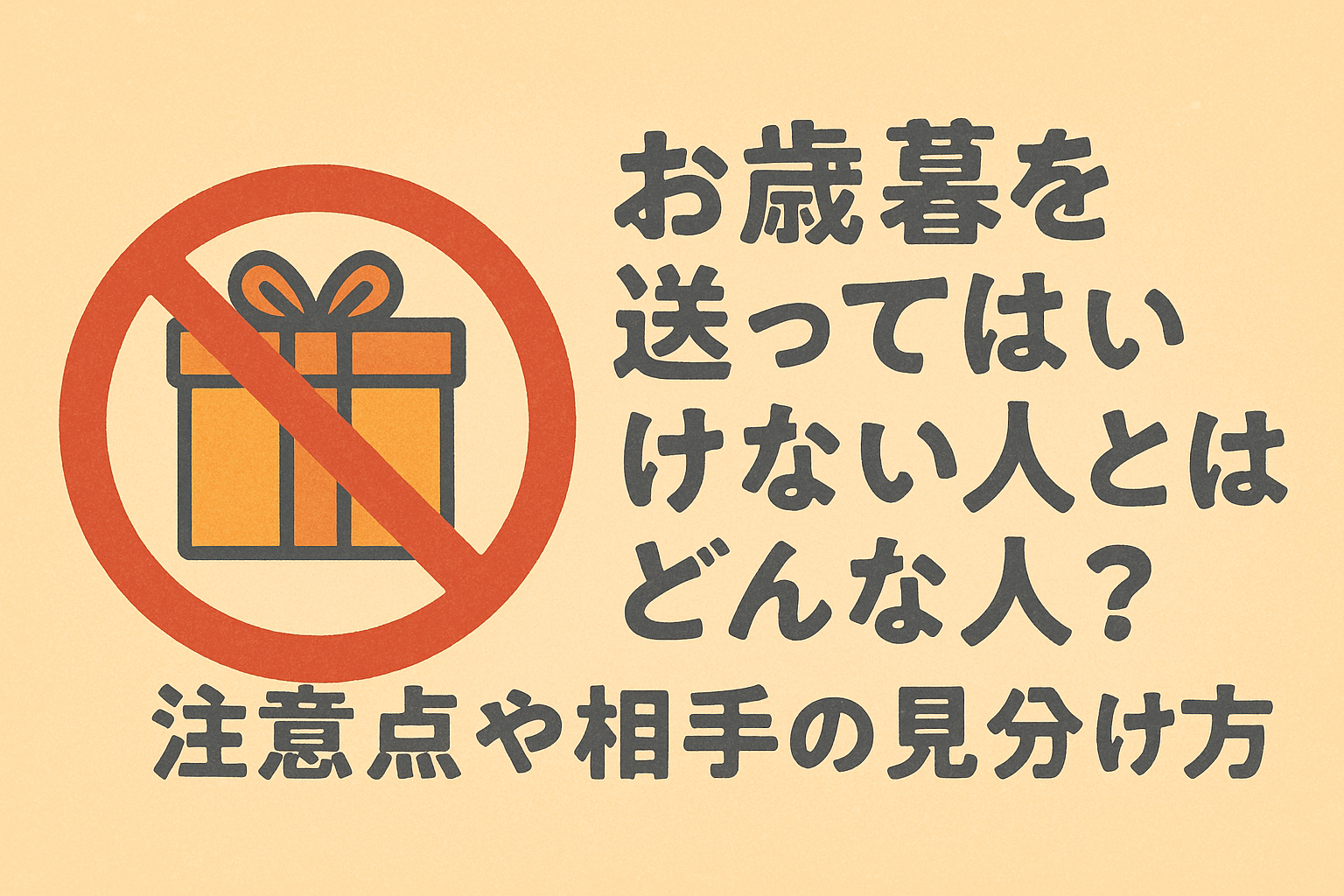
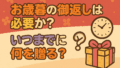
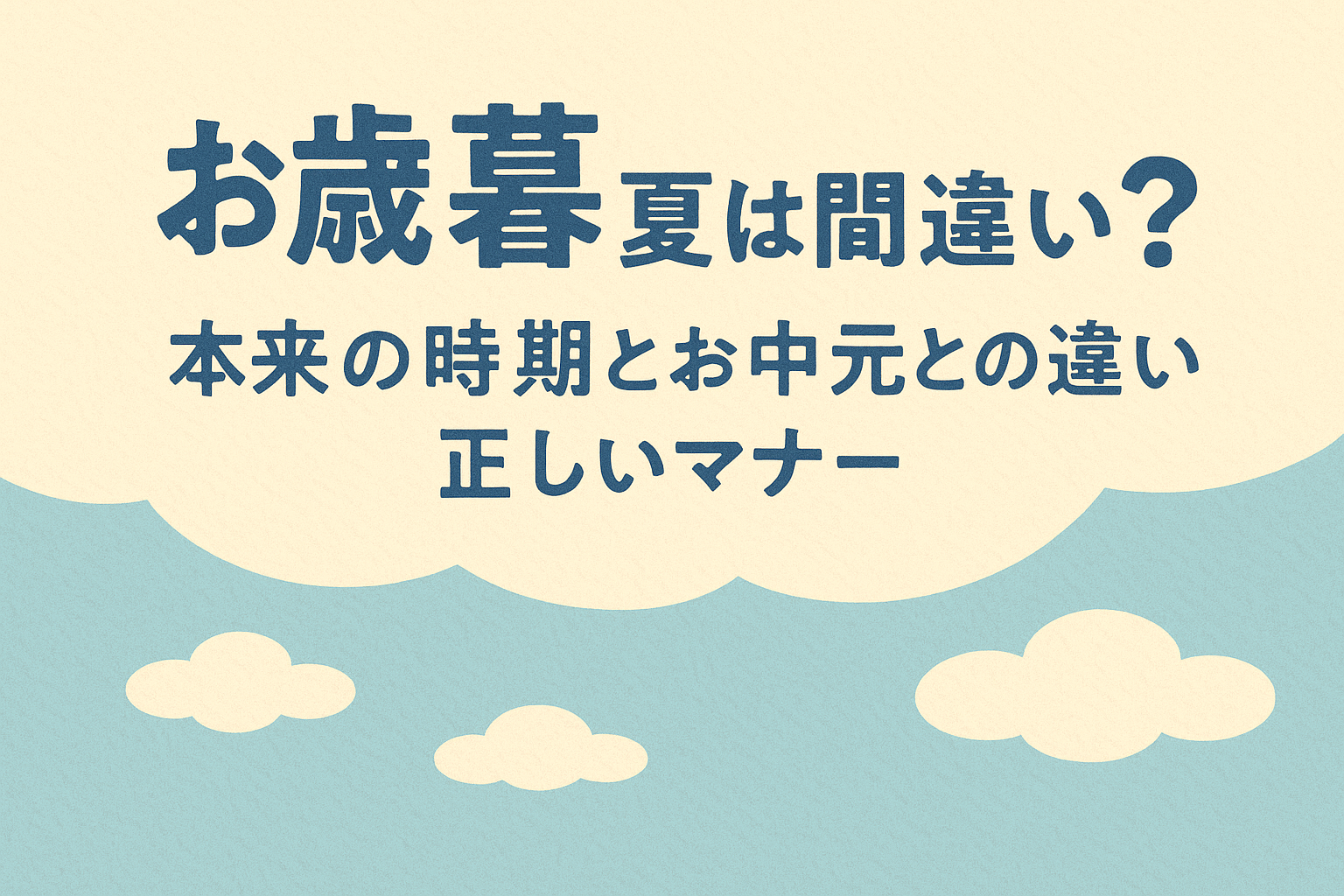
コメント