買い物前に、今日のタイムセールをチェック
いつもの食材や気になっている調味料を買う前に、
そのとき実施されているタイムセールを軽くのぞいておくと、
まとめ買いのタイミングの目安になります。
気になる人は、下のリンクから公式ページをチェックしてみてください。
※セール内容・価格・在庫状況は日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
先に結論。
「お歳暮を親戚に送るのをやめたい」場合は、お礼→次回からの辞退→今後も変わらぬお付き合いの順で、相手に合わせた手段(電話/はがき/LINE)で丁寧に伝えると角が立ちにくいです。やめどきの目安はお歳暮の時期(12月上旬〜25日頃)に入る前〜早い段階に連絡できるとスムーズです(地域差あり)。詳しい時期や表記・代替案(お年賀・寒中見舞い)も本文でやさしく解説します。
どれにしようか迷ったら、今の人気をのぞいてみる
調味料やお菓子、キッチン用品など、似たような商品が多いときは、
売れ筋ランキングで「よく選ばれているアイテム」を見ておくと、
候補をしぼるときのヒントになります。
※ランキングや取扱商品は入れ替わる場合があります。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
【結論】「やめたい」は失礼?―感謝を伝えつつ“次回から辞退”が基本
「やめる=失礼」ではありません。関係を大切にしながら見直したいなら、最初に感謝を伝え、今後はお気遣い不要(次回から辞退)の意思をやわらかく示し、最後にこれからも変わらぬお付き合いをお願いする流れが無難です。年長の親戚などには、文字だけよりも電話で落ち着いて話すほうが温度感が伝わりやすい場面もあります。文面のみの場合は、お礼→辞退→今後もよろしくの型を守ると伝わりやすくなります。
お歳暮を親戚に送るのをやめたい「やめどき」はいつ?
お歳暮の一般的な時期は12月上旬〜12月25日頃(地域差あり)。関東は12月1日〜20日頃が目安とする解説が多いです。
ベストなやめどきは、お歳暮の時期に入る前〜入りはじめに連絡しておくこと。すでに相手が用意している可能性もあるため、早めの一報が親切です。もし頂いた後なら、まずはお礼を伝えたうえで「次回から辞退」の意思をお伝えしましょう。
お歳暮の時期(目安)
・全国:12月上旬〜12月25日頃。
・関東:12月1日〜20日頃の案内が多い。
※地域差あり。年末が近づくと先方も多忙になるため、早めの連絡が安心です。
出典の多くで整合する一般的な目安です。地域の慣習に合わせてご判断ください。
買い物リストを決めたら、セールもちらっと確認
いつもの食材や日用品を買うときに、
そのタイミングで実施されているタイムセールを一緒に見ておくと、
まとめて注文するきっかけになることがあります。
気になる人は、以下から公式のタイムセールページをのぞいてみてください。
- ストック品や日用品を買う予定がある
- その日のお買い物の「ついでに」セールも見ておきたい
※セール内容・対象商品・価格などは日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
角が立たない伝え方:電話/はがき(手紙)/LINEの選び方
| 手段 | おすすめの相手・状況 | ポイント |
|---|---|---|
| 電話 | 年長の親戚・関係が近い相手 | 声で温度感が伝わる。要点メモを用意して落ち着いて話す。 |
| はがき/手紙 | 丁寧に残したい、後で文面を確認してもらいたい | お礼→辞退→今後もよろしく、の順。簡潔・平易な言葉で。 |
| LINE/メール | ふだんの連絡がデジタル中心 | まずお礼を丁寧に。要点のみ短く、失礼のない表現を。 |
ケース別の言い方・短文テンプレ(コピペ調整OK)
以下は趣旨の型です。実際には、相手との関係や言葉づかいに合わせて整えてください。
- 家計・生活の見直しを理由に
「いつも温かいお心づかいをありがとうございます。今後は行き来を簡素にし、年始のご挨拶で近況をお伝えする形に改めたいと考えております。どうかお気遣いなさらないようお願いいたします。これからも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」 - 高齢・体調面の事情
「平素よりお世話になっております。近ごろ体調の面から外出や手配が難しく、贈り物のやり取りを控えさせていただければと存じます。勝手を申しますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」 - 頂いた後に“次回から辞退”
「このたびは結構なお品をありがとうございました。今後はどうかお気遣いなく、次回からの贈り物はご辞退申し上げます。変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます。」 - 世代交代の節目
「長年にわたり心のこもったお付き合いを賜り、ありがとうございます。今後は年始の挨拶での近況報告を基本に、無理のない形で関係を続けてまいれれば幸いです。」
どれにしようか悩んだら、「今よく選ばれているもの」を見る
調味料・お菓子・キッチン用品など、似た商品がたくさんあると
どれを選ぶか迷ってしまうこともあります。
そんなときは、売れ筋ランキングで「どんな商品がよく選ばれているか」
全体の雰囲気をつかんでおくと、候補をしぼりやすくなります。
・人気のある商品をざっくり眺めたい
・他の人がどんなアイテムを選んでいるのか参考にしたい
※ランキング・取扱商品は入れ替わることがあります。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
そのまま断るのが難しい時は:お年賀・寒中見舞いに切り替える
お年賀は、正月の挨拶の意味。一般に松の内(関東1月7日頃)までに届けば失礼ではないとする解説が多いです(地域差あり、関西は1月15日とする案内も)。
寒中見舞いは、松の内が明けてから立春(2月4日頃)までの間に出すのが目安。到着が立春を過ぎる場合は余寒見舞いに切り替えます。喪中・忌中で時期をずらしたい場合にも利用されます。
| 挨拶 | 時期の目安 | 用途のヒント |
|---|---|---|
| お年賀 | 松の内まで(関東は〜1/7、地域差あり) | お歳暮の代わりに新年のご挨拶へ切替。表書きは「御年賀」。 |
| 寒中見舞い | 松の内明け〜立春頃(〜2/4前後) | 時期が遅れた時、喪中配慮にも。表記・文面に注意。 |
| 余寒見舞い | 立春後〜2月末(寒冷地は〜3月中旬の案内も) | 寒さの残る時期の挨拶。遅れたフォローに。 |
最低限のマナーおさらい(のし・お礼連絡・お返し)
- のし・表書き:一般的に「御歳暮」。時期を外したら「御年賀」「寒中見舞」など適切に切替。
- お礼連絡:頂いたら数日以内にお礼。お返しは原則不要だが、贈るなら半額〜同額程度の目安とする解説が多いです。
- 検索意図に多い疑問(「お歳暮 やめどき」「親戚 失礼」「断り方 文例」など)には、本記事のやめどき・伝え方・文例・代替案で網羅的に対応しています。
よくある質問(Q&A)
- Q. LINEだけで伝えてよい?
- A. ふだんの連絡手段がLINEなら可能です。ただし年長者には、電話→後日はがきの二段構えがより丁寧に伝わる場合があります。
- Q. 一度やめた後、再開はできる?
- A. 可能です。年始の挨拶や近況連絡を続けておくと、双方の気持ちを保ちやすく、再開もしやすくなります。確実な規程は確認できませんでしたが、慣習として柔軟に運用されています。
- Q. 喪中・忌中はどうする?
- A. 一般的には忌中は控える/時期を外して寒中見舞いへなどの配慮が案内されています。相手の状況に応じて文面と時期を選びましょう。
まとめ:円満にやめるコツ
感謝→次回から辞退→今後もよろしくの順で、相手に合わせた手段(電話/はがき/LINE)を選びましょう。
やめどきは12月上旬〜25日頃の時期に入る前〜入りはじめに連絡できるとスムーズ。難しい場合はお年賀/寒中見舞いに切り替える方法もあります。関係を大切に、年1回の季節挨拶+近況連絡へシンプル化するのも一案です。
付録:一言テンプレ(コピペ用・必要に応じて調整)
- 「いつもお心づかいをありがとうございます。今後はお気遣いには及びませんので、どうぞご無理のないようお願いいたします。これからも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」
- 「このたびは結構なお品をありがとうございました。恐縮ながら、次回からの贈り物はご辞退申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。」
※本記事は、郵便・百貨店・ギフト関連の一般的なマナー解説の整合を踏まえて作成しています。地域差や各家庭の慣習があるため、最終判断は身近な慣習に合わせてご検討ください。確実な情報が必要な場合は、最新の公式案内をご確認ください。
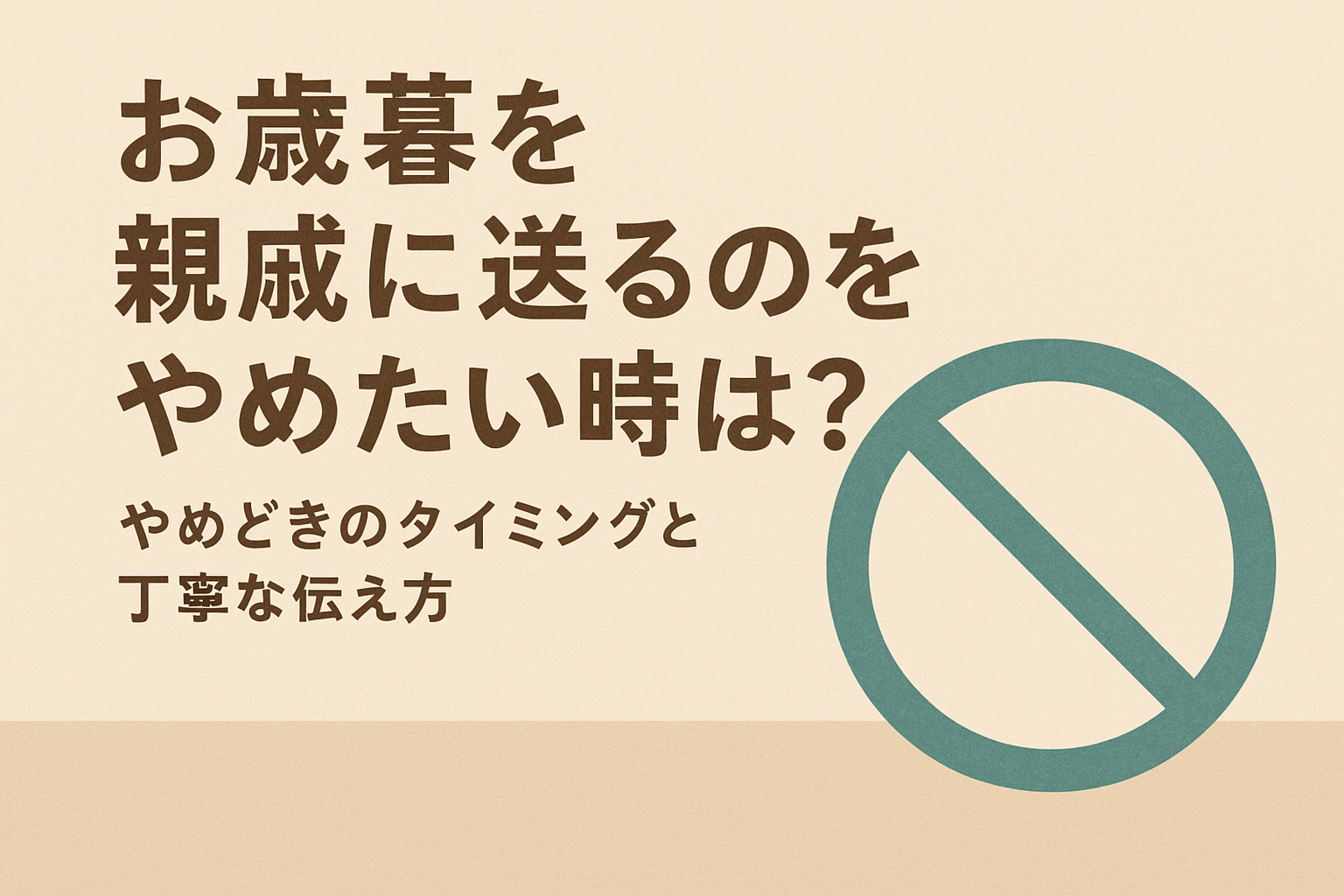
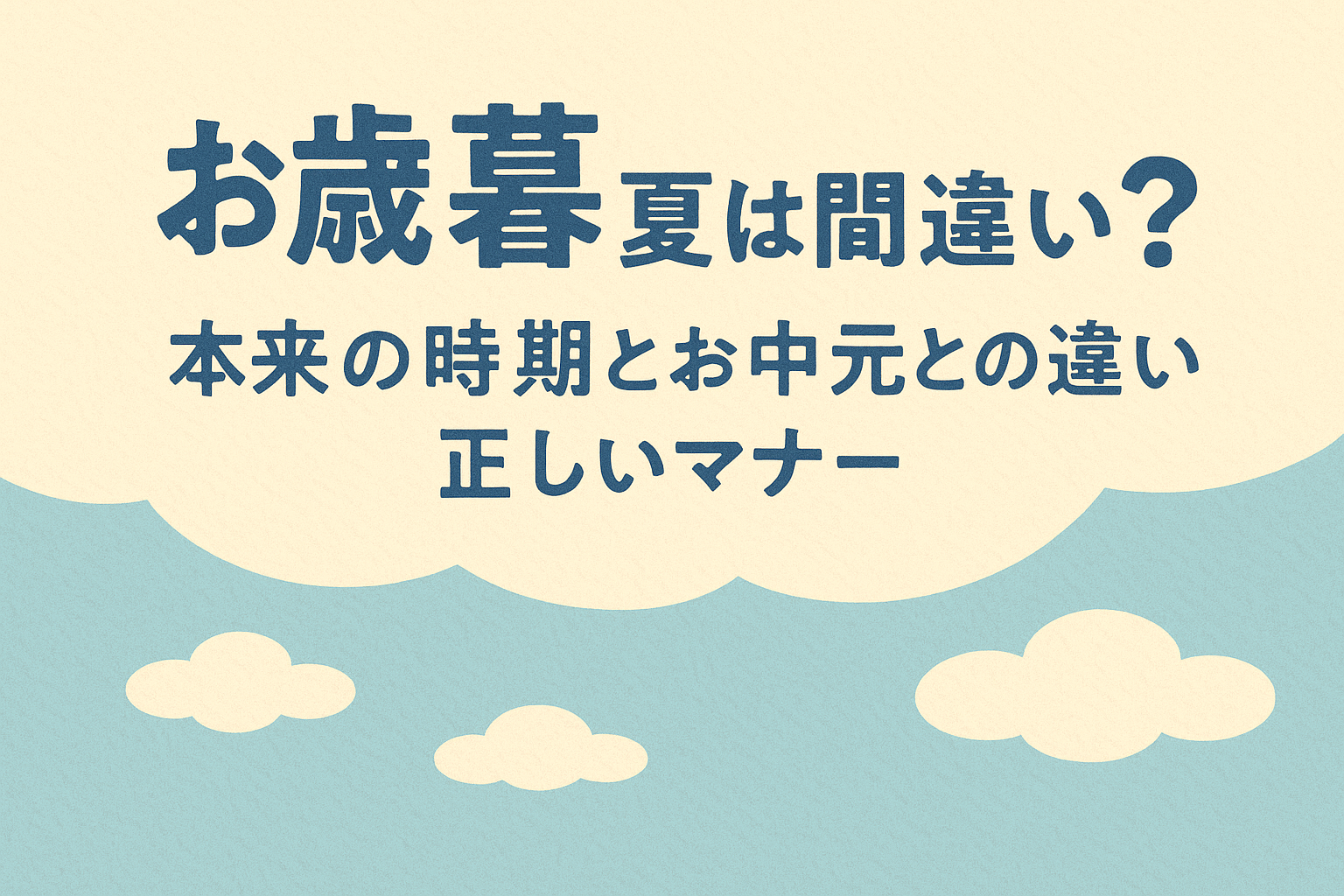

コメント