買い物前に、今日のタイムセールをチェック
いつもの食材や気になっている調味料を買う前に、
そのとき実施されているタイムセールを軽くのぞいておくと、
まとめ買いのタイミングの目安になります。
気になる人は、下のリンクから公式ページをチェックしてみてください。
※セール内容・価格・在庫状況は日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
年末が近づくと、「おせちの材料はいつ買う? 冷凍? 冷蔵?」と悩む方は多いですよね。この記事では、初めてでもわかりやすいように、「いつ」「どこで」「どのように保存するとよいか」を、食材ごとにやさしく、具体的に紹介します。買い出しスケジュールや保存のコツも載せているので、年末の準備がスムーズになりますよ。
どれにしようか迷ったら、今の人気をのぞいてみる
調味料やお菓子、キッチン用品など、似たような商品が多いときは、
売れ筋ランキングで「よく選ばれているアイテム」を見ておくと、
候補をしぼるときのヒントになります。
※ランキングや取扱商品は入れ替わる場合があります。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
結論:買い出しスケジュールと保存の基本ルール
まずは全体の目安をまとめます。おせち準備の流れを「いつ買うか」と「冷凍・冷蔵の使い分け」で把握すると、効率よく、安全に美味しく仕上がります。
- 12月上旬:乾物・調味料・保存が利く常温食材をまとめ買い
- 12月中旬~下旬:根菜や冷凍できる下ごしらえ食材を少しずつ
- 12月30~31日:鮮魚など“当日に味が映える食材”を購入
保存の基本ルールとしては:
- 冷蔵庫は7割程度の詰め込みにする
- 冷凍は−15℃以下(できれば−18℃)で保存
- 再凍結は品質を落とす可能性があるため避ける
- 調理後は小分けして急冷(冷蔵なら10℃以下)
この買い出しスケジュールと保存ルールは、主婦向けレシピサイトや政府の食品保存基準を参考に、安全性と効率を両立した方法です。
食材別ガイド:どの食材をいつ・冷凍?冷蔵?
以下では、おせちによく使われる代表的な食材ごとに、いつ買うかと冷凍・冷蔵どちらで保存するかをわかりやすくまとめます。
1. 乾物・常温で済む保存食材
例:乾燥された数の子、昆布、かつお節、干し椎茸など。これらは長く持つため、12月上旬にまとめ買いが安心です。常温で保存でき、賞味期限も長めの商品が多いため、冷蔵・冷凍の心配は基本的に不要です。ただし、購入前には商品パッケージの「保存方法」や「賞味期限」を確認しましょう。
2. 冷凍して先に準備しておける食材
例:栗きんとん、伊達巻、煮物用の下ごしらえ済み根菜など。
- 栗きんとん:ラップで包んで冷凍すると、味や食感を大きく崩さずに約1か月ほど保存できることがあります。
- 伊達巻:ラップで密封して冷凍し、同じく1か月程度の保存が可能な場合も。ただし、製品によって差があるため、商品表示を確認してください。
- 根菜(人参・ごぼうなど):あらかじめ切って下ごしらえし、小分け冷凍すると、凍ったままでも調理しやすく、味が染み込みやすくなるメリットがあります。
これらは12月中旬から下旬にかけて、少しずつ準備を進めると助かります。冷凍保存は庫内温度や密封の方法によって日持ちに差が生じるため、購入・調理する際は必ずパッケージ表示を確認してください。
3. 冷蔵で数日前から準備可能な食材
例:黒豆、味付け数の子、甘酢漬け(田作り・酢れんこんなど)などの“作り置き系”。
- 黒豆:煮汁に浸したまま冷蔵保存で、およそ5日ほどの保存が期待できます。
- 味付け数の子:密封容器に入れて冷蔵保存すると、通常は1週間程度が目安です。
- 甘酢漬け(田作り・酢れんこんなど):冷蔵で数日〜1週間ほど保存でき、しっかり味が染み込むのを待ちながら準備できます。
これらは12月30日頃までには作って冷蔵保存しておくと、お正月当日にちょうどよく味が整います。
4. 前日〜当日に買うのがおすすめの食材
魚介や練り物などは、鮮度が落ちやすいため直前に買うのが安心です。
- 海老・ぶりなどの魚介:できれば当日調理。冷蔵での保存は短期間、余った分は加熱してから冷凍(2〜3週間が目安)すると安心です。
- かまぼこ・はんぺん:未開封のものはパッケージの賞味期限を確認し、開封後は冷蔵で2日程度を目安に食べ切りましょう。冷凍は風味や食感が落ちやすいためおすすめされません。
- 生鮮野菜(ほうれん草、きぬさやなど):彩りに使う食材は大晦日に購入し、その日のうちに調理して盛り付けましょう。
買い物リストを決めたら、セールもちらっと確認
いつもの食材や日用品を買うときに、
そのタイミングで実施されているタイムセールを一緒に見ておくと、
まとめて注文するきっかけになることがあります。
気になる人は、以下から公式のタイムセールページをのぞいてみてください。
- ストック品や日用品を買う予定がある
- その日のお買い物の「ついでに」セールも見ておきたい
※セール内容・対象商品・価格などは日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
おせちの買い出しカレンダー
ここでは、年末に向けての買い物と仕込みの流れをわかりやすく時系列で整理します。
| 日付 | 買うもの・すること |
|---|---|
| 12月上旬 | 乾物(昆布、干し椎茸、数の子)・調味料(醤油、みりん、砂糖)・保存容器を準備 |
| 12月中旬 | 根菜(ごぼう・人参・蓮根)、卵、肉類を購入。下ごしらえして冷凍も可。 |
| 12月28日〜29日 | 乾物を戻す、数の子の塩抜き、黒豆の仕込みなど前準備を開始 |
| 12月30日 | 煮物、酢れんこん、田作り、黒豆などを仕上げて冷蔵保存 |
| 12月31日 | 焼き物(海老やぶり)、盛り付け、彩り野菜を調理 |
このスケジュールを目安にすれば、無理なく計画的に準備ができます。
冷蔵・冷凍保存のコツ
- 冷凍保存のコツ: 食材はできるだけ平らに伸ばしてラップや保存袋で密封し、空気を抜いてから冷凍。庫内は−18℃以下を保ち、開閉は短時間で行いましょう。
- 冷蔵保存のコツ: 庫内は詰め込みすぎず、7割程度に。保存容器は汁もれを防ぐために二重に包むと安心です。
- 小分け保存: 調理後は一度に食べきる量に分けて保存することで、衛生的で便利です。
どれにしようか悩んだら、「今よく選ばれているもの」を見る
調味料・お菓子・キッチン用品など、似た商品がたくさんあると
どれを選ぶか迷ってしまうこともあります。
そんなときは、売れ筋ランキングで「どんな商品がよく選ばれているか」
全体の雰囲気をつかんでおくと、候補をしぼりやすくなります。
・人気のある商品をざっくり眺めたい
・他の人がどんなアイテムを選んでいるのか参考にしたい
※ランキング・取扱商品は入れ替わることがあります。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 市販のおせちはどれくらい持つ?
冷蔵タイプは通常2〜3日、冷凍タイプは約1か月が目安とされる場合があります。ただし、必ずパッケージの「消費期限」や「賞味期限」に従ってください。
Q2. 前日に作っても大丈夫?
黒豆や酢の物などは前日に作って冷蔵保存しても比較的安心です。煮物も前日までに作り置き可能ですが、必ず清潔な容器に入れて冷蔵庫で保存してください。
Q3. 再凍結はできる?
再凍結は避けるのが基本です。一度解凍した食材を再び冷凍すると品質が落ちやすく、風味や食感が損なわれる可能性があります。
まとめ
「おせちの材料はいつ買う? 冷凍? 冷蔵?」という疑問に対して、ポイントは食材ごとの特徴を理解して段階的に準備することです。乾物や調味料は12月上旬に、冷凍保存できるものは中旬に、そして鮮魚や練り物は大晦日に購入する流れが基本です。
冷蔵・冷凍保存を上手に使い分ければ、年末の慌ただしい時期でも安心して準備が進められます。安全に、美味しいおせちを迎えるために、計画的な買い出しと保存方法を心がけてください。

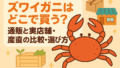
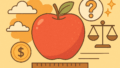
コメント