買い物前に、今日のタイムセールをチェック
いつもの食材や気になっている調味料を買う前に、
そのとき実施されているタイムセールを軽くのぞいておくと、
まとめ買いのタイミングの目安になります。
気になる人は、下のリンクから公式ページをチェックしてみてください。
※セール内容・価格・在庫状況は日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
冬の味覚の代表といえば「蟹」。その中でも「ずわい蟹」と「本ずわい蟹」の違いについて気になる方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、ずわい蟹と本ずわい蟹は同じ種類で、呼び方の違いにすぎません。
しかし、市場では「紅ズワイガニ」や「オオズワイガニ」など他の種類も存在するため、区別のために「本ずわい蟹」と呼ばれることがあります。
この記事では、ずわい蟹と本ずわい蟹の関係を中心に、見分け方や味・値段の違い、さらにブランド蟹(越前・松葉・加能)の関係についてわかりやすく解説していきます。
どれにしようか迷ったら、今の人気をのぞいてみる
調味料やお菓子、キッチン用品など、似たような商品が多いときは、
売れ筋ランキングで「よく選ばれているアイテム」を見ておくと、
候補をしぼるときのヒントになります。
※ランキングや取扱商品は入れ替わる場合があります。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
ずわい蟹と本ずわい蟹の違いは「呼び方」
「ずわい蟹」とは学名 Chionoecetes opilio の蟹の和名で、日本海やオホーツク海などで漁獲される種類です。
一方で「本ずわい蟹」という表記は、紅ズワイガニやオオズワイガニと区別するための呼称であり、実際は同じ蟹を指しています。
つまり「ずわい蟹=本ずわい蟹」と考えて問題ありません。
ただし市場や通販では「紅ズワイ」「オオズワイ」も「ズワイガニ」と表記されることがあるため注意が必要です。
ずわい蟹・紅ズワイ・オオズワイの基礎知識
ずわい蟹を正しく理解するために、他の似た種類との違いも整理しておきましょう。
| 種類 | 特徴 | 見た目の傾向 |
|---|---|---|
| 本ずわい蟹 (ズワイガニ) |
身がしっかりして旨みがある。日本海沿岸で多く漁獲。 | 生は茶色〜黄褐色、茹でると鮮やかな赤。 |
| 紅ズワイガニ | 深海に生息。水分が多くみずみずしい食感。 | 生から赤みが強い。茹でても赤。 |
| オオズワイガニ | 北太平洋に分布。やや大ぶりで希少。 | 本ズワイに似るが流通量は少なめ。 |
買い物リストを決めたら、セールもちらっと確認
いつもの食材や日用品を買うときに、
そのタイミングで実施されているタイムセールを一緒に見ておくと、
まとめて注文するきっかけになることがあります。
気になる人は、以下から公式のタイムセールページをのぞいてみてください。
- ストック品や日用品を買う予定がある
- その日のお買い物の「ついでに」セールも見ておきたい
※セール内容・対象商品・価格などは日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
見分け方のポイント
茹でるとどの種類も赤くなるため、区別が難しくなります。
そこで腹面の色を見るのがポイントです。
本ずわいは腹が白っぽいのに対し、紅ズワイは腹側も赤みを帯びています。
また、市場に出回るブランド蟹には必ず「タグ」が付けられており、産地や品質を証明しています。タグの色や形は産地ごとに違うため、チェックするのも見分けのコツです。
味と食感の違い
味については一概に優劣をつけることはできませんが、それぞれの傾向を紹介します。
- 本ずわい蟹:身がしっかりしていて甘みと旨みのバランスが良い。
- 紅ズワイガニ:みずみずしく甘みが出やすい。水分量が多め。
- オオズワイガニ:やや大きめで希少。食味は地域や個体差で変わる。
食べるシーンや調理方法(刺し、鍋、焼き)によって感じ方が変わるため、好みに応じて選ぶのがおすすめです。
どれにしようか悩んだら、「今よく選ばれているもの」を見る
調味料・お菓子・キッチン用品など、似た商品がたくさんあると
どれを選ぶか迷ってしまうこともあります。
そんなときは、売れ筋ランキングで「どんな商品がよく選ばれているか」
全体の雰囲気をつかんでおくと、候補をしぼりやすくなります。
・人気のある商品をざっくり眺めたい
・他の人がどんなアイテムを選んでいるのか参考にしたい
※ランキング・取扱商品は入れ替わることがあります。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
値段の目安と価格が変わる理由
ずわい蟹の値段は、サイズ・漁期・ブランドタグの有無などで変わります。
タグ付きブランド蟹は厳しい基準をクリアしているため、一般流通品より高値で取引される傾向があります。
例えば「加能ガニ」は甲羅幅9cm以上といった基準が設けられています。
一方、紅ズワイガニは比較的手頃な価格で販売されることが多く、家庭向けや鍋料理で人気です。
ブランド蟹(越前・松葉・加能)の関係
ブランド蟹とは、産地と規格を満たした本ずわい蟹を証明する呼称です。
- 越前がに(福井):黄色タグ。GI(地理的表示)保護制度に登録。
- 松葉ガニ(鳥取・山陰):各県タグ付き。山陰地方の本ずわいを代表。
- 加能ガニ(石川):青タグ。特に大型のものは「輝(かがやき)」と呼ばれる。
また、雌の本ずわいには地域ごとに別名があります。
福井では「セイコガニ」、石川では「香箱ガニ」、鳥取では「親ガニ」と呼ばれています。
これらも全て本ずわい蟹であり、地域性が名称に表れているだけです。
旬と漁期
本ずわい蟹の漁期は地域ごとに定められていますが、日本海側では11月6日に解禁されるのが通例です。
雄は翌年の3月ごろまで、雌は資源保護のため12月末までと短期間。
ブランド蟹はこの漁期の中で漁獲・販売されるため、旬の味わいを楽しむことができます。
まとめ
ずわい蟹と本ずわい蟹は同じ蟹ですが、紅ズワイやオオズワイと区別するために使われる呼称です。
見分ける際は腹の色やタグの有無をチェックするのがポイント。
味や値段は種類や産地、ブランド基準によって変わり、越前・松葉・加能などのブランド蟹は特に高品質とされています。
旬や漁期を意識して選べば、失敗しにくく満足度の高い買い物につながるでしょう。
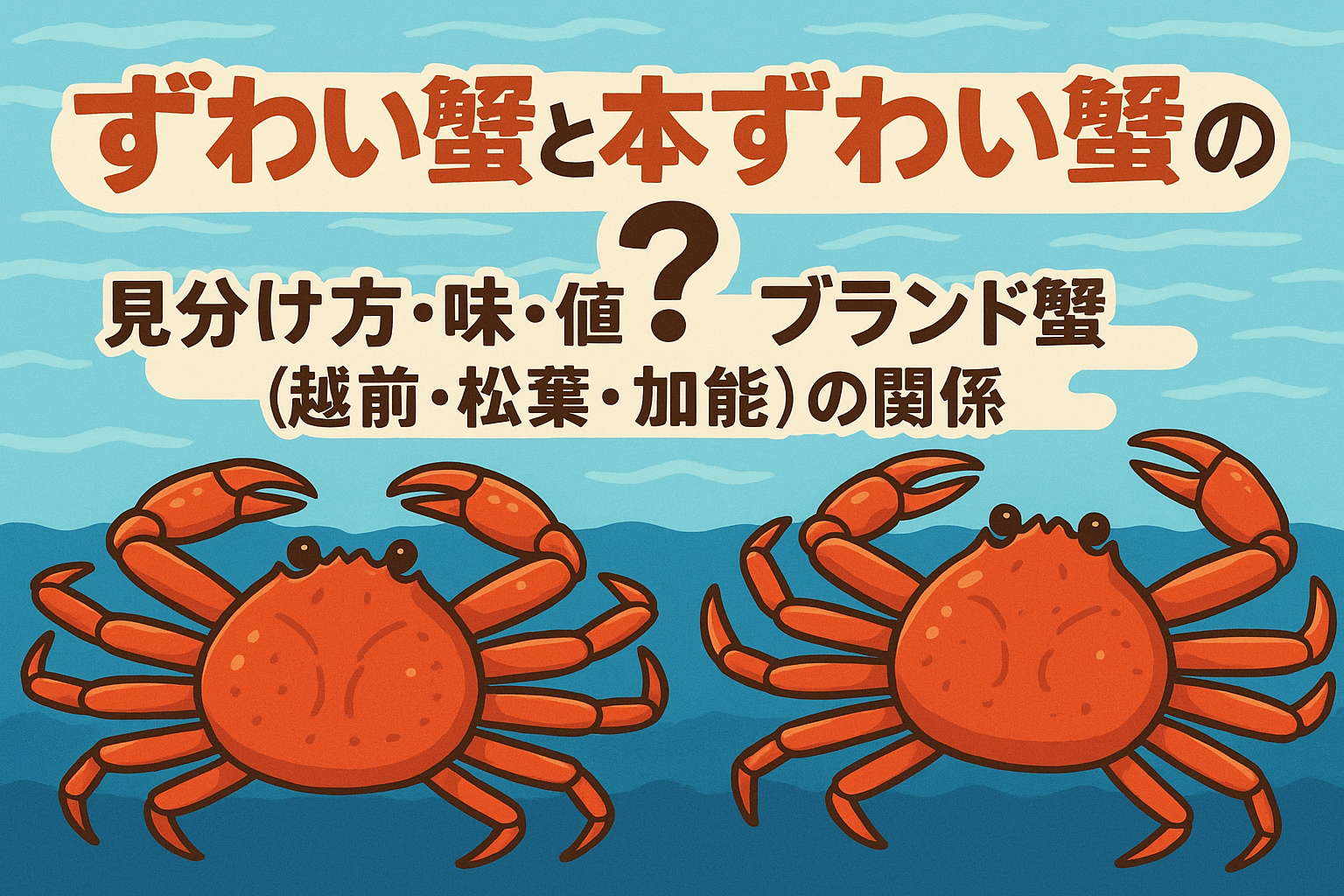
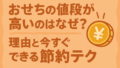

コメント