買い物前に、今日のタイムセールをチェック
いつもの食材や気になっている調味料を買う前に、
そのとき実施されているタイムセールを軽くのぞいておくと、
まとめ買いのタイミングの目安になります。
気になる人は、下のリンクから公式ページをチェックしてみてください。
※セール内容・価格・在庫状況は日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
毎年お正月に欠かせないおせち料理ですが、「おせちの値段が高い」と感じる人は少なくありません。なぜ価格が上がっているのか、その背景を知ることで納得できますし、工夫次第で節約する方法もあります。
この記事では、おせちが高くなる理由と、今日からできる節約テクニックをわかりやすく紹介します。これから予約を考えている方や、今年は少しでもお得に購入したい方に役立つ内容です。
どれにしようか迷ったら、今の人気をのぞいてみる
調味料やお菓子、キッチン用品など、似たような商品が多いときは、
売れ筋ランキングで「よく選ばれているアイテム」を見ておくと、
候補をしぼるときのヒントになります。
※ランキングや取扱商品は入れ替わる場合があります。最新の情報は各リンク先でご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
おせちの値段が高いと感じる理由
1. 原材料の高騰
おせちには数の子、えび、昆布巻き、黒豆など多くの食材が使われます。特に輸入品の魚介や牛肉などは世界的な需要や為替の影響で値段が上がることがあります。
一部の食材では値下がりも見られますが、全体としては原材料費の高止まりが続いています。
2. 資材や包装のコスト
おせちは重箱や化粧箱に入れて届けられるのが一般的です。見た目も豪華に演出するため、資材や包装費も価格に含まれています。資材の価格が上がることで販売価格も高くなりやすいのです。
3. 配送コスト(クール便)
おせちは冷蔵や冷凍の状態で配送されるため、クール便の追加料金が発生します。ヤマト運輸や佐川急便などのクール便は通常配送より数百円以上高く、全国に届けるための物流コストが価格に影響します。
4. 人件費の上昇
おせちは多くの品目を少量ずつ詰め合わせるため、盛り付けや品質管理に手間がかかります。近年は最低賃金の上昇や人手不足もあり、人件費の増加が価格を押し上げる一因になっています。
5. 品数の多さと品質管理
おせちは「少しずつ多品目」が特徴です。そのため仕込みや調理に多くの工程が必要となり、保存や検品も厳格に行われます。これらも価格に反映されています。
最新データで見るおせちの価格相場
帝国データバンクの調査によると、2025年正月向けのおせちの平均価格は約2万7,800円でした。前年に比べると値上げは続いていますが、その幅は小さくなっているとも報告されています。
一方で、高級ホテルや有名店が監修するおせちは値上げ幅が大きくなる傾向があります。その一方で、量を抑えた少人数向けやネット限定のおせちは比較的お手頃価格のものも見られます。
買い物リストを決めたら、セールもちらっと確認
いつもの食材や日用品を買うときに、
そのタイミングで実施されているタイムセールを一緒に見ておくと、
まとめて注文するきっかけになることがあります。
気になる人は、以下から公式のタイムセールページをのぞいてみてください。
- ストック品や日用品を買う予定がある
- その日のお買い物の「ついでに」セールも見ておきたい
※セール内容・対象商品・価格などは日々変動します。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
おせちの値段が高いときの節約テクニック
1. 早割で予約する
おせちは早めに予約すると割引される「早割」が多く実施されています。8月〜10月に予約すると5%〜10%割引になることもあります。予約が遅くなると割引がなくなり、人気商品は売り切れることもあるため、早めの予約がおすすめです。
2. ふるさと納税を活用
おせちをふるさと納税の返礼品として選べる自治体も多くあります。寄附金控除を利用することで、実質的な自己負担を抑えられる場合があります。ただし、受付締切や配送日が決まっているため、早めにチェックする必要があります。
3. 人数や段数を見直す
豪華なおせちは魅力ですが、人数に対して大きすぎると食べ残しが出てしまいます。最近は一人用や少人数用の「食べきりサイズ」も人気です。無駄を減らすことで支出も抑えられます。
4. 冷凍と冷蔵の違いを理解する
冷蔵おせちはできたてに近い状態で届きますが、受け取り日の都合が合わないと不便です。冷凍おせちは解凍の手間があるものの、受け取り日を選びやすいのが利点です。ライフスタイルに合わせて選ぶことで、食品ロスや余計な出費を減らすことにつながります。
5. ポイント還元やキャンペーンを利用
通販サイトでは、キャンペーン期間に合わせて購入するとポイント還元が受けられることがあります。クレジットカードのポイントやネットモールのセール時期を組み合わせるとさらにお得です。
Q&Aでよくある疑問を解決
Q1:おせちの相場は?
平均は2万円〜3万円台が多く、豪華なおせちは5万円を超える場合もあります。内容や監修するお店によって大きく変わります。
Q2:早割はいつから?
多くの百貨店やスーパーは8月〜10月ごろに早割を開始します。特に人気商品は早期に売り切れるため、早めに予約しておくと安心です。
Q3:ふるさと納税で注文できる?
はい。ふるさと納税の返礼品として用意している自治体があります。ただし、数量や受付期間が限られているため、ポータルサイトで確認しましょう。
どれにしようか悩んだら、「今よく選ばれているもの」を見る
調味料・お菓子・キッチン用品など、似た商品がたくさんあると
どれを選ぶか迷ってしまうこともあります。
そんなときは、売れ筋ランキングで「どんな商品がよく選ばれているか」
全体の雰囲気をつかんでおくと、候補をしぼりやすくなります。
・人気のある商品をざっくり眺めたい
・他の人がどんなアイテムを選んでいるのか参考にしたい
※ランキング・取扱商品は入れ替わることがあります。最新の情報は各リンク先の公式ページでご確認ください。
※本ページには広告が含まれています。
まとめ|理由を知れば節約もできる
おせちの値段が高い背景には、原材料費や人件費、配送コストなど複数の要因があります。しかし、早割やふるさと納税を利用したり、人数に合ったサイズを選んだりすることで、賢く節約することは可能です。
年末に慌てる前に、早めに情報を集めて予約しておくことで、家計にやさしく、美味しいお正月を迎える準備ができます。
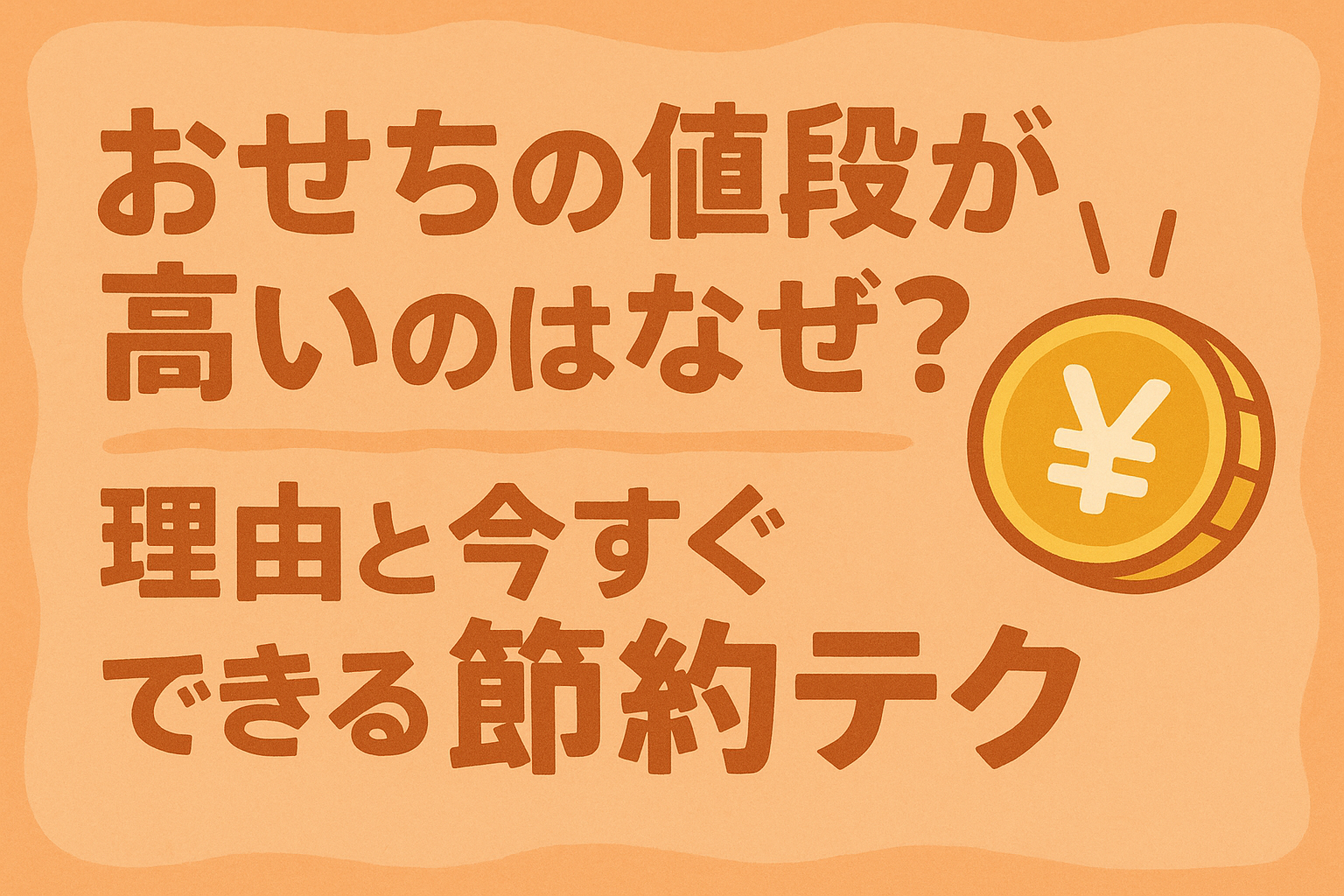
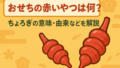
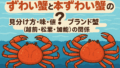
コメント